1989年3月、アヤトッラー・ホメイニーがサルマン・ラシュディに『悪魔の詩』のために死刑宣告を出した後すぐに、ロンドンの『オブザーバー』紙は、パキスタンからの匿名の投書を掲載した。その中で、執筆者は名前を明かさないムスリムで、「サルマン・ラシュディは私のために語っている」と述べていた。その後、彼は次のように説明した。
私のものは、新聞コラムでいまだ見出されなかった表現という声です。ムスリムに生まれたが、成人して放棄したいと望む人々の声です。しかし、死の痛みに関して、未だ許されていないのです。
イスラーム社会に暮らしていない人には、その制裁が想像できません。自分で強制したものであれ、外部から強制されたものであれ、宗教的な不信仰を表明することに対して、影響を及ぼすのです。「私は神を信じていません」は、家族や友人の中でさえ、不可能な公の発話です。...それで、我々の中で誰が疑っているか、黙っています。
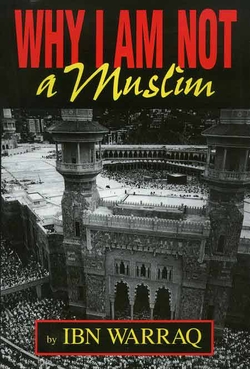
「イブン・ワラク」は、もはや黙らないことを決めた。今ではイスラーム共和国と呼ばれた国で育ち、現在、オハイオで暮らし、教えている男としてのみ身元を明らかにして、ホメイニーの命令があまりにも彼を憤慨させたので、神聖冒涜に関して、『悪魔の詩』を超越する本を書いた。ラシュディは魔術的なリアリズムの軽薄な話において、どこでつかみどころのない批評を提供したか?イブン・ワラクは、イスラームをくつがえすという課題に学究的な大槌をもたらす。イスラームに対して論争を書くことは、特にムスリム出生の著者にとって、あまりにも煽動的な行為なので、著者は偽名の下で書かなければならない。そうしないことは、自殺行為であろう。
そして、聞いてもらえないこの反抗的態度の行為のために、何をイブン・ワラクは示す必要があるのか?充分に調査され、全く見事で、もし幾らか秩序が乱れたとすれば、世界の大宗教の一つの告発である。著者が独創性に対するいかなる口実も否認する反面、彼が去った信仰を表現している、驚かせる小説を提供するエッセイを書くには、充分広く読んできた。
まず始めに、イブン・ワラクは、ムハンマドが一度も存在しなかったか、あるいは、もし存在したならば、彼はクルアーンと何ら関係がなかった、という驚くべき主張をする現行の西洋学術を利用する。むしろ、あの聖なる書は一世紀か二世紀後にパレスチナで偽造され、その後、「発明されたアラビアの起源点に企画した」。もしクルアーンが欺瞞ならば、イスラーム伝統の他の部分で、著者がほとんど正真正銘だと思っていないことを知って、驚くべきではない。例えば、彼は「イスラーム法の全体」を「偽造と敬虔なフィクションに基づいた素晴らしい創造」だと片付ける。イスラームの全体を、要するに、彼は嘘のでっち上げだと描写するのである。
かくして宗教を不要にしてきたので、イブン・ワラクは歴史と文化を取り上げる。政治的公正さをまさに全く間違って使いながら、彼は初期イスラームの征服者を非難し、欧州の植民地主義を容赦する。「アラビアに向かって一日に五度頭を下げることは」と、メッカに向かうイスラーム祈祷に言及しつつ、彼は書く。「確かに、文化帝国主義の...究極の象徴でなければならない」。対照的に、欧州の支配は「あらゆる欠点と共に、究極的には支配者と同程度に多く、被支配者を益した。ある悪名高い事件にも関わらず、欧州権力は自らを、全体として、非常に人間的に行なった」。
中世期のイスラーム文明の到達がイスラームの偉大さを示すという慣習的な議論に対して、イブン・ワラクは、クルアーンやイスラーム法のためではなく、それにも関わらず、イスラーム文明が存在するようになったというヴィクトリア議論を回復させる。科学や芸術における刺激は、ムスリム世界の外部から来た。イスラームが統治したところは、イスラーム当局の圧力が回避され得た場でのみ、これらの達成が起こった。中世の文化的栄光のためにイスラームを信用することは、ガリレオの発見のために異端審理裁判所を信用することのようであろうと、彼は信じている。
現在に戻ると、ムスリムは、近代化しようとする多大な労苦を経験してきたと、イブン・ワラクは論じる。なぜならば、イスラームは彼らの方法で堅固に立っているからだ。その逆進的な志向は変化を困難にする。「全ての革新は、イスラームにおいて落胆させられる。あらゆる問題は、社会あるいは経済の問題としてよりも、むしろ宗教問題として見られる」。この宗教は、提供する機能的なものは何もないように思われることだろう。「イスラーム、特に政治的イスラームは、現代世界と社会的、経済的、哲学的な付帯問題の全部に対処することに、全く失敗してきた」。著者は、改善のための希望も約束しない。国家から個人を保護する問題を取れ。「国際人権に向けてのいかなる動きにとっても、イスラームにおける主要な障害は、神であるか、もっと正確に述べると...コーランとスンナという源泉への崇敬である」。
特別に微妙な章で、自身が西洋で暮らしているムスリムであることを考慮して、イブン・ワラクは、欧州や北米へのムスリム移住を議論する。彼はイスラーム方法の輸出に関して懸念し、移民の要求に譲歩せず、伝統的な諸原則に堅く忠実であるよう、英国人に助言する。ムスリムの影響によって「大警戒が行使されない限り、我々は皆、英国社会が大いに道義的に貧窮したと思うことがあり得るであろう」。同時に、リベラルで西洋志向にふさわしいムスリムとして、イブン・ワラクは、鍵となる境界線は個人の哲学の一つであり、(サミュエル・ハンチントンが確言するような)宗教的な執着ではない、と論ずる。「最終的な闘いは、必ずしもイスラームと西洋の間ではなく、自由に価値を置く人々と置かない人々の間であろう」。この議論は、多様な信仰の人々が共通項を見出せるという含みを持たせながら、事実、希望を差し出す。
全体として、イブン・ワラクのイスラーム査定は、例外的に厳しい。その宗教は、欺きに基づいている。攻撃性と威嚇を通して成功した。進歩を抑止する。そして、それは「全体主義の型」である。歴史の十四世紀近くを調査して、彼は結論づける。「コーランの教えの効果は、人間の理性、社会、知的、道義的進歩にとって災難であった」。
これがあたかも充分ではないかのように、イブン・ワラクは、「一神教的傲慢さ」と自分が呼ぶものに対する急襲で冒涜を仕上げ、宗教でさえそのようにする。彼は幾つかの興味深い問い、西洋の我々がもはや尋ね合わないように思われる種を尋ねる。「もし多神教から一神教への自然な展開があるならば、一神教から無神論への自然な発展というものはないのか?」神がぼんやりした場や陰気な環境に現れる代わりに「なぜ彼は自身をサッカー競技場でワールド・カップのファイナルの間に大衆に露わにできないのか?1917年に、ポルトガルのファティマの奇跡よりもむしろ、なぜ彼は西部戦線で大虐殺を終わらせなかったのか?」
この議論は、まさにどれほどこれらの諸問題が、主流のアメリカ知識人の生活において、もはや議論されないかを指摘する。信仰者と無神論者は、討論に関与することなしに他者を中傷しながら、それぞれ別の道を行く。この理由で、イブン・ワラクの反宗教発言の多くは、驚くべき新鮮な特徴を持つ。
非ムスリムにとって、イブン・ワラクが犯した反則を充分に評価することは、困難である。というのは、深い抗議や驚愕すべき挑発という彼の本は、我々の無鉄砲な文化において、想像可能ないかなるものをも超えているからだ。我々は、およそイスラームに比肩し得る敬神を持っていない。例えば、宗教的な領域で、ジョセフ・ヘラーは1984年の小説『神のみぞ知る』で、幾つかの聖書物語をポルノグラフィ的な乗客に転換したが、誰も気づきさえしなかった。1988年の映画『キリストの最後の誘惑』におけるイエスの性的な憧れ描写で、マルティン・スコーシーズは少数の監視員に直面したが、確かに命に脅威はなかった。ラシュディ自身は最近、原理主義ヒンドゥ教徒の指導者のバル・サッカレイをからかうことで、インドで怒りと憎しみの感覚を上げてきたが、その方面から何ら危難は来なかった。政界では、チャールズ・マレーやデニッシュ・デソウザが、非常に最もデリケートなアメリカの話題、異なった民族の能力という問題に関する本を出版したが、いずれも結果として隠れる必要がなかった。
対照的に、イスラームに対する冒涜は殺人へと導く。そして、ただサルマン・ラシュディにとって、あるいは、エジプトやバングラデッシュのような場所においてのみならず。少なくとも、このような処刑は、アメリカの土地で発生してきた。アリゾナ州ツクソンで暮らしているエジプト人の生化学者ラシャド・ハリファは、コンピュータでクルアーンを分析し、幾ばくかかなり複雑な数秘学から、第九章の最後の二節が聖なる書に属さないと結論した。この洞察は、事実上、彼自身が預言者であると宣言するよう促した。(ムハンマドが最後の預言者であると奉じる)イスラームにおける非常に深刻な反則である。数ヶ月後の1990年1月31日に、知られざる論敵が、思うに正統派ムスリムであろうが、彼の教えに怒り、ハリファを刺して死なせた。その件は未解決のままであるが、明らかにぞっとするようなメッセージを送った。合衆国内でさえ、逸脱は死へと導く。
イスラームに非友好的だとされた著述家は、始終、殺害される。エジプトやトルコでの卓越した著述家と同様に、何ダースものジャーナリストがアルジェリアで命を落とした。タスリマ・ナスリンは、この理由で出生地のバングラデッシュを逃げなければならなかった。この種の本が西洋でのみ出版できるように、ひどい沈黙がムスリム世界に降りて来た。
この文脈で、イスラームの教義に同意しない権利というイブン・ワラクの主張は、衝撃である。そして、失礼な態度で西洋人の権利でさえそうすると彼が主張する時、尚一層そうである!「本書は、いの一番に、イスラームにおける何でもかんでも批判する私の権利の断言である-冒涜、誤りを犯すこと、風刺、嘲りのためでさえ」。『なぜ私はムスリムでないのか』は、確かに嘲る特徴を有するが、真剣で思考を挑発する本でもある。沈黙の壁を要求するのではない。ましてや、著者の命に対するラシュディのようなファトワでもない。信じているムスリムからの等しく強制的な応答を要求するのである。

